「御霊前」と「浄土真宗」にまつわる慣習やマナーについて、悩んでいませんか。
宗派ごとに異なる香典の書き方やマナーについて、正しく理解していないと、失礼にあたるのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、御霊前や浄土真宗の葬儀における正しい香典の使い方から具体的なマナー、表書きの選び方、そして金額の相場や書き方まで、誰もが疑問に感じやすい点について分かりやすく解説します。
大切な故人やご遺族に対して誠意を持って対応できるよう、押さえておきたいポイントをまとめました。
正しい知識を身につけ、自信を持って御霊前や浄土真宗の葬儀マナーを実践しましょう。
御霊前と浄土真宗における使用法

御霊前は日本の仏教や宗派において故人への供物や弔意を示す表書きのひとつです。
しかし、宗派ごとに細かな違いがあり、特に浄土真宗では独自の考え方があります。
それぞれの宗派に合ったマナーを知っておくことで、誤った作法を避けることができます。
御霊前とは何か?意義と使用場面
御霊前とは、通夜や葬儀など、故人への弔意を表す際に香典袋の表書きとして使われる言葉です。
この表書きは、主に仏教の宗派で用いられ、故人の魂が成仏するまでの間に供えるものとされています。
お通夜や葬儀の際に参列者が持参する香典袋に「御霊前」と書くことで、亡くなった人への哀悼の気持ちを表現します。
キリスト教や神道でも似たような慣習がありますが、表記が異なる場合があります。
浄土真宗における御霊前と御仏前の違い
浄土真宗では、「御霊前」と「御仏前」に明確な違いがあります。
本来、御霊前は亡くなった人がまだ仏様になっていない状態と考えられている間に使用する言葉です。
しかし、浄土真宗の教義では、人は亡くなるとすぐに仏様、すなわち阿弥陀仏の元へ往生すると説かれています。
そのため、浄土真宗では葬儀でも「御仏前」と表記することが一般的です。
| 表書き | 使用場面 | 宗派の考え方 |
|---|---|---|
| 御霊前 | 他宗派の通夜・葬儀 | 成仏前の故人に供える |
| 御仏前 | 浄土真宗の葬儀・法事 | 故人はすぐ仏様になる |
このように、表書きの意味と使用場面、宗派ごとの教えによって選ぶ言葉が異なります。
浄土真宗の葬儀での表書き選び
浄土真宗の葬儀に参列する際は、香典袋の表書きには「御仏前」と書くのが正しい作法です。
他にも「御香資」「御香典」といった表書きが使われる場合もありますが、やはり最も正式なのは「御仏前」です。
- 直系の親族や近親者は特に「御仏前」が望ましいです。
- 故人が浄土真宗である場合、通夜・葬儀ともに「御仏前」と記載しましょう。
- 不明な場合は、あらかじめ喪主や葬儀社に確認するのも安心です。
浄土真宗の教義を理解し、それに合った表書きを選ぶことが大切です。
御霊前が使用されない理由
浄土真宗で御霊前が使われないのは、「故人は亡くなった瞬間に阿弥陀仏の浄土へ往生し、仏になる」という根本思想によるものです。
そのため、「御霊前」は成仏前の魂に対して用いる言葉であり、浄土真宗では適さないとされています。
これは単なるマナーの問題だけでなく、宗派の価値観や大切にしている信仰からきているルールです。
遺族や親族、参列する方々の気持ちに寄り添うためにも、浄土真宗では「御仏前」を選ぶようにしましょう。
浄土真宗の葬儀におけるマナーと作法

浄土真宗の葬儀は、他の宗派とは異なる特徴や作法が多く存在します。
遺族や参列者が正しいマナーを守るためには、浄土真宗ならではのポイントを理解しておくことが大切です。
故人やご遺族への敬意を示しつつ、宗派の作法に則った行動を心がけましょう。
葬儀の流れと特徴
浄土真宗の葬儀は、「仏教葬」と呼ばれる儀式の中でも特徴的です。
主な流れは、導師の入場、読経(正信偈や和讃)、お焼香、故人への念仏の称名があります。
故人が仏になると考えられているため、極端な悲しみを避けて、念仏を通して故人を偲ぶことが重視されます。
また、「引導渡し」という儀式は行わず、あくまで念仏を称えることが中心です。
故人の安らかな極楽往生を願う点も、他の宗派と違う大きな特徴といえるでしょう。
- 導師入場後、参列者は静かに席で待機
- 読経の間は姿勢を正して聴聞
- お焼香は順番に案内に従って行う
- 念仏や和讃は一緒に唱えても問題ありません
浄土真宗のお焼香の作法
浄土真宗のお焼香には、独特の作法があります。
他の宗派では抹香を額にいただく場合がありますが、浄土真宗では抹香をいただかず、そのまま香炉にくべるのが基本です。
一般的には、一回の焼香(本山式)または二回の焼香(地方による)で、回数は地域や家の流儀により異なることもあります。
| 宗派 | 焼香の回数 | 抹香の扱い |
|---|---|---|
| 浄土真宗 | 1回または2回 | 額にいただかない |
| 他の宗派 | 2~3回 | 額にいただく場合あり |
多くの場合、お焼香の順番は喪主やご遺族が最初に行い、続いて親族や参列者が案内に従います。
また、お焼香の際には静かに心を込めて行うことがマナーです。
浄土真宗のお悔やみの言葉
浄土真宗ではお悔やみの言葉選びにも注意が必要です。
「ご冥福をお祈りします」「安らかにお眠りください」といった表現は、浄土真宗の教義にそぐわないとされています。
これは浄土真宗では「故人はすでに仏(成仏)となり、浄土へ往生している」と考えられるためです。
適切な言葉の例としては以下のようなものがあります。
- 「このたびはご愁傷様でございます」
- 「お悔やみ申し上げます」
- 「ご遺族の皆さまのご健康をお祈り申し上げます」
宗派独自の考え方を尊重し、場にふさわしい表現を心がけましょう。
数珠の使い方と注意点
浄土真宗の数珠は宗派独自の形状や持ち方が定められています。
主に「本式数珠」と呼ばれるもので、輪が二重になっているのが特徴です。
数珠を使う際には、左手で持ち、合掌するときは両手に掛けて両手を合わせる形が正式とされています。
右手だけで持つ、またはぶら下げたままなどはマナー違反となることがあるためご注意ください。
また、他宗派の数珠を使うこともマナー違反ではありませんが、可能であれば浄土真宗用を用意するとより好印象です。
葬儀の場では数珠がアクセサリーではなく、念仏を唱える際の大切な仏具であることを忘れずに扱いましょう。
御霊前香典の金額と書き方の注意
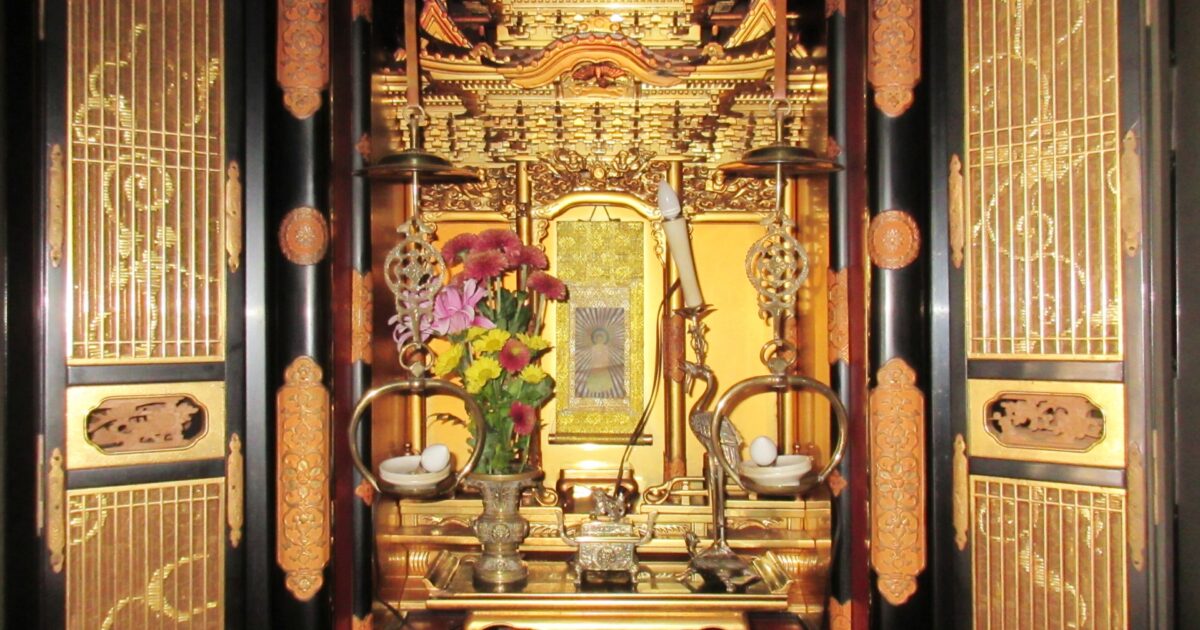
御霊前に包む香典の金額や、浄土真宗における書き方には特有のマナーがあります。
相手のご遺族に失礼のないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。
相場と故人との関係性による違い
香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢、地域の習慣によって異なります。
目安としては、近親者であれば1万円から3万円、親しい友人や知人の場合は5千円から1万円程度が一般的です。
会社関係の上司や同僚、友人であれば3千円から1万円の範囲がよく選ばれています。
- 両親・兄弟姉妹:1万円~5万円
- 親戚:1万円~3万円
- 友人や知人:5千円~1万円
- 会社関係:3千円~1万円
ただし、地域によっては相場が異なることもあるため、心配な場合は両親や周囲の大人に相談しましょう。
外袋・内袋への正しい記入方法
香典袋には「外袋」と「内袋」があり、それぞれに記入する内容や書き方もポイントです。
まず、外袋の表書きですが、浄土真宗では「御霊前」ではなく「御仏前」とするのが正しいマナーです。
| 袋の種類 | 表書き | 書く内容 |
|---|---|---|
| 外袋 | 御仏前(浄土真宗) | 表中央に表書き、下段に自分の氏名 |
| 内袋 | ― | 裏面に金額・住所・氏名 |
外袋の表中央には「御仏前」と記入し、その下に自分の氏名を書きます。
内袋には金額を旧字体や漢数字で書くのが好ましいです。例:「金壱万円」や「金五千円」となります。
裏面には住所と名前を明記し、連絡先も書いておくと親切です。
薄墨を用いる理由とその意味
香典袋に名前や表書きなどを記入する際、薄墨を使うのが一般的です。
これは「涙で墨が薄まりました」「突然の訃報で、きちんと黒い墨をすれなかった」という意味が込められています。
特にお通夜や葬儀当日は薄墨がよく使われますが、四十九日以降や法事では通常の濃い墨でも問題ありません。
浄土真宗の場合も、この薄墨の風習は変わりません。
マナーとして形式に従いつつも、心を込めて故人を悼む気持ちが何より大切です。
香典を渡す際のマナー

香典を渡す際には、宗派や地域のしきたりを重んじることが大切です。
浄土真宗では一般的な仏教マナーと異なる部分があるため、注意が必要です。
故人や遺族の心に寄り添い、失礼のないよう細やかな心遣いを心がけましょう。
香典袋の選び方と購入場所
浄土真宗の場合、香典袋は「御仏前」と書かれたものを選ぶのが適切です。
「御霊前」は浄土真宗の教えでは使わないのが一般的ですので、間違えないよう注意しましょう。
香典袋は文房具店やスーパー、コンビニエンスストアなどで手軽に購入できます。
また、ネットショップでも宗派別に対応した香典袋が販売されています。
- 文房具店:専門的な品揃えがあり安心
- スーパー:急な用意にも便利
- コンビニ:24時間対応で深夜や早朝でも入手可能
- ネットショップ:宗派別やデザインにこだわった商品が豊富
購入の際は、包装紙の色や水引(白黒・双銀)も確認しましょう。
香典の包み方とお金の入れ方
香典は新札を避け、できればピン札ではなく一度折ったお札を用意すると良いとされています。
お金の入れ方にはルールがあり、表面と裏面の向きや入れる枚数にも注意を払いましょう。
下記の表に包み方のポイントをまとめました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| お札の向き | 肖像画が裏側を向くように入れる |
| お札の端 | 封を開けたときにすぐ出てこない側を上にする |
| 入れる枚数 | なるべく奇数枚になるよう工夫する |
包む前に手を清潔にし、丁寧な気持ちで準備しましょう。
御霊前を渡す際の心得と言葉遣い
浄土真宗では「御霊前」の表書きは適さないため、事前に遺族の宗派を確認しましょう。
香典を渡すときは、ご遺族に対し丁寧な言葉遣いでお悔やみの気持ちを伝えます。
言葉に迷ったときは、下記のようなフレーズが一般的です。
- 「このたびはご愁傷様です」
- 「心よりお悔やみ申し上げます」
- 「本当に突然のことで…」
宗派によってNGワードもあるため、浄土真宗では「冥福」や「成仏」の言葉は使わないよう注意しましょう。
小声で穏やかに伝えることで、遺族への配慮も伝わります。
袱紗に包む理由とその使い方
香典を袱紗に包むのは金封を汚さず、きちんとした印象を与えるためです。
袱紗は落ち着いた紫や紺、緑色など慶弔両用のものを選びます。
使い方にも次のようなポイントがあります。
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| 1. 香典袋を袱紗の中央に置く | たたみやすい位置を確認 |
| 2. 袱紗の右側→下→上→左の順で折る | 左側が最後になるように折る |
| 3. 渡す直前に静かに取り出す | 机などの上で袱紗から出して渡す |
袱紗の扱いも含めて、丁寧な所作を心がけることがマナーアップにつながります。
御霊前と浄土真宗についての理解を深めて

御霊前と浄土真宗について理解を深めることで、法要やお参りの際に正しいマナーを守ることができます。
これまでにご紹介した内容を参考にして、慌てることなく心を込めて弔意を伝えることができるでしょう。
浄土真宗ならではの考え方や香典の表書きの違いなどは、とても大切なポイントです。
周囲の方への配慮や故人への思いが、こうしたマナーの中にも込められています。
不安なときや迷ったときには、信頼できる人や寺院の方に相談するのが安心です。
大切な人への供養を心から行うためにも、今回ご紹介した内容をぜひ今後に役立ててください。


