大切な人を送り出す最後の時間、故人への想いを伝えるために「棺掛け」をどのように選べばよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
宗教や地域、そして時代によってその種類や意味合いが異なり、棺掛け選びには意外と知られていない決まりや配慮が求められます。
この記事では、棺掛けの歴史や役割、宗教ごとの特徴から、現代的なデザインや選び方、価格の目安、購入方法まで幅広くお伝えします。
大切な場面で後悔しないよう、ぜひこの記事を参考にしてください。
棺掛けとは何か?その役割と意味

棺掛けは、日本の葬儀の中で重要な役割を持つ伝統的な風習です。
故人が安らかに旅立てるように、棺に掛けられる布や装飾品を指します。
棺掛けには、故人や遺族の想いが込められており、厳粛な雰囲気を演出する大切な意味が込められています。
棺掛けの基本的な意味と歴史
棺掛けは、古くから仏教や神道の儀式の中で用いられてきた習慣です。
元々は、故人を守るための清めや、魂が穢れなく浄土へ旅立てるよう願う意味合いが込められていました。
江戸時代には、家紋や宗派の模様が刺繍された特別な布が使われることが一般的となり、各家庭や地域によって棺掛けのデザインにも違いが生まれました。
現代においても、その基本的な意味は変わらず受け継がれています。
| 時代 | 棺掛けの特徴 |
|---|---|
| 江戸時代 | 家紋や宗派の模様が主流 |
| 明治時代 | 装飾性が高まり多様化 |
| 現代 | シンプルなデザインやオーダーメイドが増加 |
納棺や棺周りのしきたりを具体的に把握したい場合は、納棺の儀とは何かや手順・副葬品の選び方まで徹底解説で実際の手順や由来を確認してみてください。

棺掛けの役割と重要性
棺掛けは、葬儀の進行において複数の役割を担っています。
- 儀式の厳粛さを高める役割
- 家族や親族の気持ちの整理を助ける象徴的意味
- 宗教的・文化的なしきたりの継承
また、棺掛けを選ぶ際には、宗教や地域の習慣に合わせるほか、故人の趣味や人生観を反映させることも重視されています。
棺掛けは単なる装飾品ではなく、亡くなった方に対する深い敬意や、遺族の思いやりを表現する重要なアイテムです。
宗教的な意味合いや儀礼の背景をより深く知りたい方は、お経をあげないと成仏できない?自分でお経をあげる方法も解説を参照すると、読経の役割や実践方法がよくわかります。
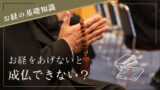
宗教別に見る棺掛けの種類と特徴

棺掛けは、お葬式や告別式の際に棺桶の上にかける装飾布のことで、故人への敬意や宗教的な意味合いが込められています。
宗教の違いによってそのデザインや使われ方も様々です。
主な宗教ごとに棺掛けの特徴や選び方を見ていきましょう。
仏教式の場合の棺掛け
仏教式の棺掛けは、最も目にすることが多いスタイルの一つです。
主に白や紫といった厳粛な色合いを用い、蓮の花や菊の模様など、仏教を象徴するモチーフが施されています。
山型に折りたたんだ形にして、棺桶の正面に美しく見えるように掛けるのが一般的です。
多くの場合、戒名や故人の名前、生前の功績を記した刺繍が入れられることもあります。
香やお線香を添えることも、仏教式特有の習慣です。
- 白を基調とした布地
- 蓮や菊などの伝統柄
- 宗派による模様や色使いの違い
- 経文や戒名の刺繍を施す場合も
仏教式の服装や死装束との関係も気になる場合は、白装束と死装束の違いを徹底解説で服装の意味や選び方を確認しておくと参考になります。

神道における棺掛けの特徴
神道では「御棺帷子」と呼ばれる白い布がよく使われます。
神道の教えに従い、清浄さが重んじられるため、無地でシンプルなデザインが一般的です。
刺繍や柄はほとんどなく、装飾よりも潔白を意識した作りになっています。
また、神主による祝詞奏上の時にも棺掛けが重要な役割を果たします。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 色 | 主に白色でシンプル |
| 素材 | 麻や絹などの自然素材 |
| 装飾 | 無地、またはごく控えめ |
神道特有の作法や忌中の扱いについて知りたい方は、神棚封じの正しいやり方と意味で実務的な注意点や手順をチェックしておくと安心です。

キリスト教式での棺掛けの選び方
キリスト教式のお葬式では、「パリオ」と呼ばれる棺掛けが使用されることが一般的です。
白や紫、青など、教派や式の性質によって色が選ばれます。
十字架や天使、鳩など、キリスト教らしいデザインが特徴です。
教会によっては、教会備え付けのパリオを使う場合もあります。
オリジナルの刺繍や、故人のイニシャルを入れるなど、個別のアレンジも可能です。
その他の宗教における棺掛け
イスラム教やユダヤ教など他の宗教でも、それぞれ独自の棺掛けや遺体の覆いがあります。
例えば、イスラム教では「カーファン」と呼ばれる白布で遺体全体を包みますが、日本国内でのお葬式では宗教や地域の習慣にあわせて工夫されています。
宗教ごとに求められる決まりや美意識が異なるため、故人やご遺族の信仰に合わせて適切な棺掛けを選ぶことが大切です。
また、宗教儀式以外にも無宗教の自由葬などでは、特にこだわりなく好きな柄や色の棺掛けを選ぶケースも増えています。
現代における棺掛けのデザインと選択肢

棺掛けはご遺体を収めた棺の上に掛ける布であり、古くから日本の葬送文化で大切な役割を担ってきました。
近年では伝統を大切にしながらも、時代や価値観の変化に合わせてデザインや素材の選択肢が広がっています。
棺掛けのあり方はご遺族の想いを表現する手段となっており、より個性的で温もりのあるものを選ぶ人も増えています。
伝統的なデザインと現代的なアプローチ
棺掛けのデザインは、日本の伝統的な文様や宗教的なモチーフを用いたものが一般的でした。
例えば蓮や菊といった植物柄や、御仏をイメージさせる模様が多く見られます。
一方で、現代ではカラーバリエーションや柄の種類が豊富になり、個人の趣味や個性に合わせた棺掛けも登場しています。
- 無地やパステルカラーのシンプルな棺掛け
- 四季を感じさせる花柄をあしらったデザイン
- 家紋やイニシャルなどを刺繍したオリジナル棺掛け
伝統を大切にしつつも、今の家族に寄り添う新しいスタイルが選ばれています。
素材による違いと選び方
棺掛けにはさまざまな素材があり、それぞれに特徴やメリットがあります。
素材の選択によって、見た目や肌触りだけでなく、全体の雰囲気も大きく変わります。
| 素材 | 特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| 絹 | 光沢があり高級感がある | 格式のある葬儀や伝統を重んじる家庭に |
| 綿 | 柔らかくナチュラルな風合い | 温かみや優しさを重視したい方に |
| ポリエステル | 耐久性に優れ扱いやすい | お手入れしやすいものを求める方に |
素材選びは、ご遺族の希望や葬儀の雰囲気、予算などを考慮しながら行うとよいでしょう。
装飾的な意味合いが増す棺掛け
以前は形式的な役割が強かった棺掛けですが、現在では装飾的な意味合いも増しています。
特に、色彩豊かなデザインや個性あふれるモチーフが選ばれることで、棺掛け自体が故人へのメッセージや感謝の印として機能することがあります。
一部では、写真や思い出の品をあしらった特注の棺掛けも登場し、ご遺族が積極的に関わってデザインを考えるケースも見られます。
棺掛けは、故人の人生や人柄、家族の想いを表現する大切なアイテムとなってきています。
棺と棺掛けの価格範囲と選び方

棺と棺掛けはお葬式で欠かせない大切なアイテムです。
素材やデザイン、必要となる宗派や地域の風習によって、その価格や選び方には幅があります。
ご家族の希望や予算に合わせて、事前にしっかりと情報収集し適切なものを選ぶことが、後悔のないセレモニーのためには大切です。
棺掛けの価格帯と選択肢
棺掛けの価格帯は、使用する生地の種類やデザインの凝り度合いによって異なります。
シンプルな無地の棺掛けであれば数千円から用意できるものもありますが、刺繍が施されていたり、上質な素材を使っているものは1万円以上することもあります。
選択肢としては、以下のようなバリエーションが一般的です。
- 無地タイプ(シンプルで予算を抑えたい方におすすめ)
- 宗教ごとに異なる絵柄や刺繍入りのタイプ
- 高級感のあるベルベットやサテン生地のもの
- オーダーメイドで家紋や特別なデザインの入ったもの
宗派ごとの決まりやご家族の意向を確認したうえで、用途やデザインに合った棺掛けを選びましょう。
棺と棺掛けのセットの相場
棺と棺掛けをセットで用意する場合、単品で購入するより費用が抑えられることがあります。
一般的なセットの価格相場は、以下の表のとおりです。
| セット内容 | 価格帯 |
|---|---|
| シンプルな棺+無地の棺掛け | 5万円~10万円 |
| 装飾あり棺+刺繍や柄入り棺掛け | 10万円~20万円 |
| 高級棺+特注デザイン棺掛け | 20万円以上 |
予算やご希望に合わせて無理のないセットを選ぶことが大切です。
葬儀社によってはプランにセット料金が含まれている場合もあるため、事前に内容を確認しましょう。
棺掛けに関するQ&A

棺掛けは、ご葬儀の際に故人の棺の上に掛ける布のことです。
地域や宗派、葬儀の形式によって使われる棺掛けのデザインや素材は異なります。
ここでは、棺掛けの購入方法やカスタムオーダーについてご紹介します。
棺掛けはどこで購入できるのか?
棺掛けは様々な場所で購入することが可能です。
一般的に以下のような方法があります。
- 葬儀会社や葬祭場での取り扱い
- 仏具店や冠婚葬祭専門店での購入
- インターネット通販サイト(Amazon、楽天市場など)
- 手作りやオーダーメイド業者への依頼
多くの葬儀会社では棺掛けがセットになっている場合が多いですが、希望に合わせて単品購入も可能です。
また、地域に根付いた仏具店では伝統的なデザインやオリジナル商品の取り扱いが豊富です。
インターネット通販では、デザインや素材の種類も多く、価格や納期を比較しながら選ぶことができます。
手作りやオーダーメイドを希望の場合、布地やデザインの相談ができる点が魅力です。
葬儀会社や仏具店、オーダー業者の選び方で迷ったら、葬儀社の選び方の記事を参考に比較ポイントを押さえておくと選定がスムーズになります。
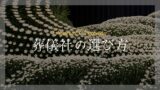
カスタム棺掛けの注文方法
自分だけの特別な棺掛けを用意したい場合は、カスタムオーダーもおすすめです。
ここでは、一般的なカスタム棺掛けの注文の流れについて表でご紹介します。
| 手順 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1. 問い合わせ | 希望する業者や店舗に連絡し相談します。 |
| 2. デザイン打ち合わせ | 色・柄・生地・サイズなどを相談して決定します。 |
| 3. 見積もり | 仕様に応じた料金や納期を確認します。 |
| 4. 注文・製作 | 内容に納得したら正式に注文し、製作を進めてもらいます。 |
| 5. 納品 | 完成した棺掛けが指定した場所に届きます。 |
カスタムの場合、納期がかかることも多いため、余裕を持って相談することが大切です。
希望のデザインがある場合は、イメージ画像や参考写真を用意しておくとスムーズです。
素材やデザインによって価格も大きく異なるため、事前にしっかり見積もりを取りましょう。
棺掛けと葬儀の関係を理解する

ここまで葬儀に関するさまざまなポイントについて触れてきましたが、棺掛けもまたその一つの大切な要素です。
棺掛けとは、葬儀の際に棺の上から白い布や絹をかける行為を指します。
この行為は故人への敬意を表し、最期の旅立ちを清らかに見送るという意味が込められています。
宗教や地域によって呼び方や方法が少し異なる場合もありますが、大切な人を丁寧にお送りする気持ちは共通しています。
葬儀の中で行われる棺掛けは、ご遺族や参列者が心を込めて故人に手を合わせる時間でもあります。
また、棺掛けを行うことで「役目を終えた」という区切りの役割を担うこともあります。
葬儀の形式が多様化する現代でも、棺掛けの温かい意味合いは受け継がれています。
大切な別れの場面で、棺掛けの意義を知っておくことで、より心のこもったお見送りができるでしょう。


