”
大切な人を送り出す最後のとき、副葬品の選び方に悩む方も多いのではないでしょうか。
「どの副葬品がおすすめなのか」「何を入れてよいのか不安」「故人や家族が後悔しない選択をしたい」といった思いに直面する場面だからこそ、正しい情報が必要です。
この記事では、副葬品おすすめの選び方や、入れて良いもの・避けるべきもの、準備のポイントまで分かりやすく解説します。
心を込めて見送りたい…そんなあなたのために、適切な副葬品選びのヒントをお伝えします。
副葬品のおすすめ選び方
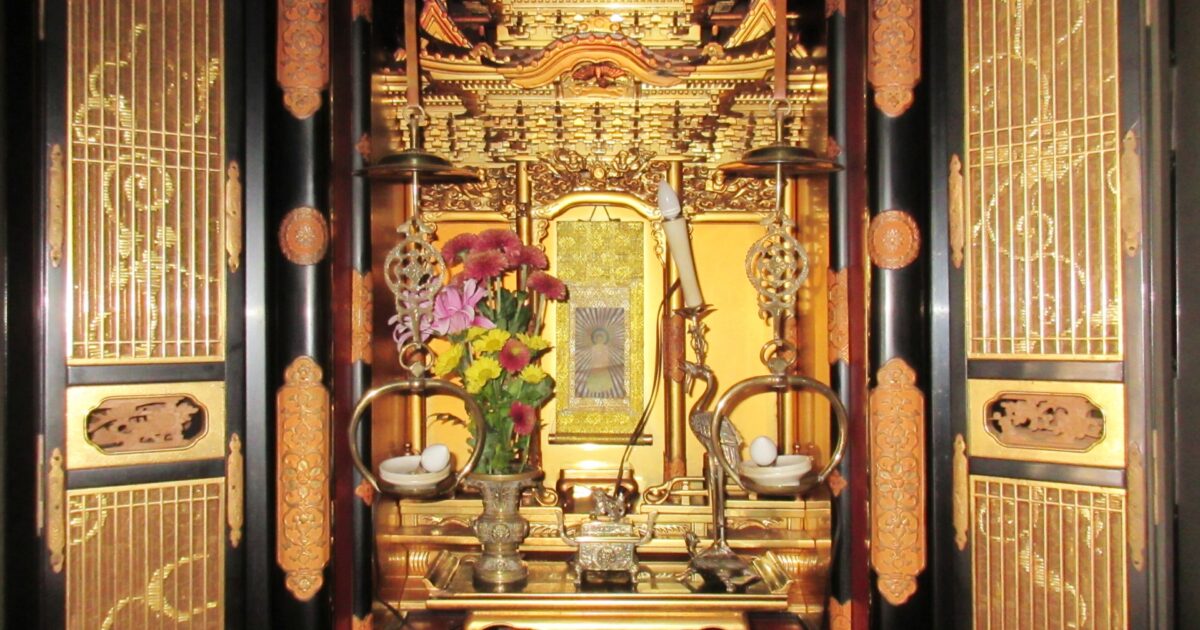
副葬品は故人との最後のお別れの大切な品です。
選ぶ際には、故人らしさや家族の思いを大切にしながら、適切な品を選ぶことが大切です。
ここでは、副葬品を選ぶ際に心がけたいおすすめのポイントをご紹介します。
故人の好みを考慮して選ぶ
副葬品を選ぶ際、故人が生前に好んでいたものを思い出してみましょう。
例えば、好きな色や趣味、お気に入りの衣服や小物など、故人らしさが伝わる品を選ぶと心のこもったお見送りになります。
- 趣味の道具や愛用品
- 普段よく身につけていたアクセサリー
- 好きだった音楽CDや本
- 思い出の写真
こうしたアイテムを副葬品として選ぶことで、故人を偲ぶ気持ちがより深まります。
故人の思い出の品物を選ぶ
故人と家族や友人との思い出が詰まった品物も、副葬品としておすすめです。
旅行で手に入れた記念品や、手作りの作品、長年愛用していた小物などが該当します。
| 品物の種類 | 思い出の例 |
|---|---|
| 旅行の写真 | 家族旅行の記念や楽しかった思い出 |
| 手作りの作品 | 共同で作った物や故人の手仕事 |
| 学生時代の品 | 卒業アルバムや勲章などの記念品 |
何気ない日常の一部だった品々に、かけがえのない思い出が詰まっています。
故人への感謝の気持ちを表現するものを選ぶ
これまでの感謝の気持ちを表すために、手紙やメッセージカードを副葬品にする方も多くいます。
感謝の言葉や想いを書いた手紙や写真入りのカードなど、気持ちが伝わるものは故人への最後の贈り物として喜ばれます。
また、家族みんなで寄せ書きをするのも良いでしょう。
直接手渡しできないからこそ、素直な気持ちを込めて副葬品にすることが大切です。
家族の意見を取り入れる
副葬品を選ぶときは、家族や親しい方々の意見も大切にしましょう。
故人について家族それぞれが思い描くイメージや、思い入れのある品について話し合うことで、より納得のいく副葬品選びができます。
みんなで話し合うことで、知らなかった故人の一面を知るきっかけとなることもあります。
家族全員の気持ちが込められた品物は、心温まるお別れになります。
火葬に適した材料を確認する
副葬品を選ぶ際には、火葬時に問題がないかを必ず確認しましょう。
金属製品やガラス製品は火葬炉を傷める可能性があるため、ほとんどの斎場で持ち込みができません。
布や紙、木製の品など燃やしても安全な素材の物を選ぶことが大切です。
火葬場によって細かなルールが異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
安心して大切な副葬品をお見送りできるよう、きちんと準備をしておきたいですね。
入れて良い副葬品とは

副葬品とは、大切な方が亡くなった際に一緒に棺に納める品物のことです。
故人への想いを形として残すために、副葬品を選ぶご遺族も多くいらっしゃいます。
入れて良い副葬品は、地域や宗教、斎場の決まりによってさまざまです。
火葬場によっては持ち込みが制限されているものもあるため、事前に確認することが大切です。
ここでは、多くの方が選ばれている代表的な副葬品についてご紹介します。
手紙や寄せ書き
手紙や寄せ書きは、副葬品として特に人気の高いもののひとつです。
家族や友人が故人へメッセージを書き、最後の思いを伝えます。
心のこもった言葉を書いた手紙は、故人への想いを伝える大切なお別れの品となります。
紙製品は火葬にも適しているため、安心してお入れいただけます。
- お孫さんからの絵手紙
- 家族や親しい友人のメッセージカード
- 感謝の手紙
- 生前の思い出話を綴った寄せ書き
故人が愛した服や小物
故人が生前大切にしていた服や小物も、副葬品として選ばれやすいアイテムです。
愛用の帽子やハンカチ、愛着のあるアクセサリーなど、小さな品であれば火葬に支障がないことが多いです。
特に綿・麻素材の服や、布製の小物は安全に納めることができます。
| 副葬品例 | おすすめポイント |
|---|---|
| ハンカチ | 思い出の品として火葬にも問題ありません |
| メガネケース | メガネは不可ですが、布ケースは可の場合が多いです |
| セーター | 天然素材なら問題なし。ただしボタンや金具は避けましょう |
生前のお気に入りの写真
故人が生前に好んでいた写真も、副葬品としてよく選ばれます。
家族写真や旅行の思い出の一枚など、人生の大切な場面を共にできるアイテムです。
紙製の写真は燃え残りにくく、安全に火葬できます。
アルバムごとは不可な場合が多いので、一枚ずつ選んでお入れしましょう。
趣味に関連するアイテム
故人の趣味がわかるアイテムも人気の副葬品です。
趣味の道具は故人らしさが込められており、ご遺族の思い出も詰まっています。
ただし、大きな物や金属製・プラスチック製の物は入れられませんので、注意が必要です。
例をいくつかご紹介します。
- 釣りが趣味だった方なら、布製の釣り帽子や手ぬぐい
- 手芸好きだった方なら、自作の小さな作品
- 文房具好きの方には、紙のしおりやメモ帳
故人が望んだ食べ物や飲み物
生前に好きだったお菓子や飲み物を副葬品として入れる方もいらっしゃいます。
紙に包んだ飴や、小さな袋入りのお菓子などは火葬でも安心です。
ペットボトルや缶などの容器は不可のため、中身だけを小袋に入れるなど工夫しましょう。
大切なのは、故人が喜ぶ顔を想いながら選ぶお気持ちです。
副葬品として避けるべきもの

副葬品を選ぶ際には、故人を偲ぶ気持ちは大切ですが、火葬場でのルールやマナーに配慮することも必要です。
誤ったものを副葬品として入れてしまうと、火葬時にトラブルになる恐れや、他の方に迷惑がかかる場合もあります。
ここでは副葬品として避けるべき主なものについて説明します。
燃えにくい素材のもの
火葬の際に燃えにくい素材は、焼却が難しく残りやすいため推奨されていません。
例えば革、プラスチック、厚手の布、化繊、ゴム製品などがあります。
- 厚手のぬいぐるみ
- 靴や鞄
- ダウンジャケット
- 合成皮革のカバンや財布
- ビニール系の小物
これらは火葬後も燃え残りが出て、仕上がりに悪影響を与えることがあるため注意しましょう。
有害物質を発生するもの
火葬の際に有害なガスや成分が発生するものは、火葬場の環境や作業員に悪影響を及ぼすため、絶対に入れないようにしましょう。
スプレー缶、ペンキ、ライター、電池などは特に危険です。
| 対象物 | 理由・リスク |
|---|---|
| スプレー缶 | 爆発・有害ガス発生の危険性 |
| 電池類 | 破裂の恐れ、発火・爆発のリスク |
| ライター | 発火や爆発事故の原因になる |
| ペンキ類 | 有毒物質を発生する可能性 |
他にも、化粧品やリチウムイオン電池を含む電子機器も発火・有害ガスリスクがあります。
大量の水分を含むもの
果物や飲み物、ゼリーなど、大量の水分を含むものは火葬の進行を妨げる場合があります。
水分が多い副葬品は、火力を下げる原因となったり、燃焼に時間がかかったりするため、一般的には控えた方がいいでしょう。
金属やガラス製のもの
指輪や時計、メガネ、ガラスの小物など、金属・ガラス製品は火葬後に骨壺の中に残ってしまうことがあります。
これらは処理も難しく、遺骨の取り扱いにも支障をきたします。
特別な事情がない限り、副葬品として金属やガラスを選ばないようにしてください。
貨幣や新札
副葬品として現金や新札、貨幣を入れるのはマナー違反とされています。
実際の貨幣や新札は金属やインクを含み、火葬後に形が残るため衛生面・管理面で問題があります。
副葬品には代用品の紙幣デザインの紙などを使うことをおすすめします。
入れられない副葬品の代替案

副葬品には法律や火葬場のルールで入れることができない品物もあります。
しかし、どうしても故人に思い入れのあるものを手向けたい場合には、いくつか代替案があります。
これらの工夫をすることで、大切な思いを無理なく伝えることが可能です。
写真を撮って棺に納める
持ち込めない副葬品がある場合は、その品物の写真を撮影しプリントしたものを副葬品として棺に納める方法があります。
大切な品や思い出の品と一緒に旅立つ気持ちを伝えることができ、火葬場でも安心して受け入れてもらえます。
写真に残すことで、形のあるものに気持ちを託せる点もおすすめポイントです。
- 思い出の品を写真に収める
- 故人のお気に入りの風景やペットの写真もOK
- カメラやスマホで簡単に準備可能
ミニチュアや模型を作成
副葬品の代わりとして、オリジナルのミニチュアや模型を作成して棺に入れるのも人気です。
例えば、長年愛用していたゴルフクラブや楽器などの本物は入れられなくても、小さな模型やミニチュアなら可能な場合がほとんどです。
| ミニチュア例 | おすすめ理由 |
|---|---|
| ゴルフクラブの模型 | 趣味の思い出を形で遺すことができる |
| ぬいぐるみのミニチュア | 大事な物を小さくして持たせられる |
| 模型のカバン | 思い出のアイテムとして安心して副葬できる |
専門業者にオーダーしたり、手作りすることで、より気持ちのこもった副葬品になります。
故人の思いを込めた絵を入れる
思い出の品や伝えたい気持ちを絵にして託す方法もおすすめです。
プロの画家だけでなくご家族やお孫さんが描いた絵でもよく、色紙などに描いて棺に入れることで、心温まるお別れができます。
お子さんによるメッセージ入りの絵や、家族写真をアート化したものも喜ばれます。
絵には誰でも自由に思いを託せるという良さがあります。
火葬後に骨壺に納める
どうしても火葬できない副葬品の場合、火葬後にお骨と一緒に骨壺へ納める方法もあります。
例えば、金属製のアクセサリーやお守りなどは火葬前に棺へ入れられませんが、火葬後であれば骨壺に入れて保管できます。
火葬後に納めるアイテムは次のようなものが該当します。
- 指輪やペンダントなどの貴金属
- お守りや小さな手紙
- 特別な小物類
ただし、納骨堂や墓地の規則によって制限がある場合もあるため、事前に確認しましょう。
副葬品 おすすめの選び方

副葬品の選び方は、故人や家族の想いを大切にしながらも、宗教的・文化的な背景や実際の葬儀の流れを考慮することが大切です。
後悔のないお別れを実現するために、ポイントをしっかり押さえましょう。
故人の希望を最優先する
副葬品を選ぶうえで最も大切なのは、故人の生前の希望や想いを第一に考えることです。
生前に「好きだったもの」や「大切にしていた品」があれば、それらを副葬品として選ぶのがよいでしょう。
迷った場合は、遺族や親しい友人に故人が望んでいたものについて相談するのもおすすめです。
故人の趣味や好きな食べ物、愛用していた日用品など、思い出深いものほど心を込めて選ぶことができます。
- 生前愛用していたもの
- 趣味に関するアイテム
- 手紙やメッセージ
- お気に入りのぬいぐるみや写真
家族の心を繋ぐ選び方
副葬品は、家族や親族にとっても大切な役割を果たします。
例えば、家族全員で手作りした手紙や折り紙などを副葬品にすると、故人への感謝や愛情が伝わりやすくなります。
また、お孫さんが描いた絵なども心温まる選択です。
家族の心が一つになれるような副葬品を選び、みんなで故人を偲ぶことで、心の整理につながります。
| 副葬品の例 | 特徴 |
|---|---|
| 手紙 | 故人への想いを形にできる |
| 家族写真 | 思い出を共有できる |
| 折り紙 | 皆で作って一体感が得られる |
| 似顔絵 | 子どもたちの気持ちが伝わる |
葬儀社のアドバイスを活用する
副葬品に関して、不安や迷いがある場合は葬儀社のスタッフに相談するのが安心です。
地域ごとの風習や宗教的な決まりごと、安全面(焼却可能なもの・不可能なもの)など、具体的なアドバイスを受けられます。
葬儀社によっては、副葬品として持ち込めるもの、持ち込めないもののリストを用意している場合もあります。
事前に確認しておけば、当日のトラブルも防げます。
適切なタイミングでの副葬品準備
副葬品は葬儀の直前や、通夜の前までに準備しておくのが理想的です。
遅れてしまうと、慌ただしくなったり、大切な品物を忘れてしまうこともあります。
事前に家族でリストを作成し、役割分担を決めておくと無理なく準備できます。
納棺のタイミングは葬儀の進行によって異なるため、事前に葬儀社や担当者に副葬品の持ち込みや手順を確認しておくと安心です。
“


