盛籠料の書き方に悩む方は少なくありません。
最近の生活習慣や宗教観の多様化により、「これで正しいのか」と不安を抱く場面も増えていることでしょう。
この記事では、盛籠料に関するポイントを押さえ、正しい書き方やマナーを学ぶことで、失礼のないふるまいを身につけるお手伝いをします。
基本的な知識から表書きの選び方、贈る際のマナーまで幅広く解説いたしますので、自信を持って故人を偲ぶ心を伝えましょう。
盛籠料の書き方を知るための基本知識

盛籠料は、主に葬儀や法要の場で贈られる物品を指し、弔意や感謝の気持ちを伝える手段として用いられます。
供物としての役割を持ち、贈る側と受け取る側の信仰や習慣に基づいて内容や贈り方が異なります。
適切に盛籠料を準備することで、相手に対する敬意を正しく伝えることが可能です。
盛籠とは何か?その役割と意味
盛籠とは、供物の一種であり、葬儀や法事の際に故人へ供えるための籠を指します。
故人の冥福を祈る目的で贈られるもので、果物やお菓子、缶詰などが詰められることが一般的です。
贈ることで遺族への弔意を示すための重要な役割を持ちます。
類似する供え物との違いや自宅での飾り方を比較したい場合は、陰膳とは何かを徹底解説で各供え物の扱いやマナーを詳しく説明しています。

宗教や宗派による盛籠の中身の違い
盛籠の中身は、宗教や宗派によって選ばれる品物が異なることがあります。
- 仏教では精進料理の観点から動物性食品を避けることがあります。
- キリスト教では葬儀における供物の習慣が少ないため、シンプルな花かごを選ぶことが多いです。
- 神道では厳格なルールはありませんが、酒や米などが供えられることがあります。
宗派ごとの具体例や実際の慣習が気になる場合は、キリスト教の葬儀におけるマナーでキリスト教側の供え物の扱いを確認しておくと参考になります。

盛籠を贈る際のタイミングと適切なタイミング
盛籠を贈るタイミングは、主に次のような場面で行われます。
- 通夜の日
- 葬儀または告別式の日
- 法事や年忌供養の際
葬儀の前か当日に会場へ届けるように手配するのが一般的です。
遅れてしまうことのないよう、事前に準備をしておくことが大切です。
通夜や葬儀の到着時間に迷ったら、実際の時間感覚や参列の目安をまとめたお通夜の時間についてを参考にして届くタイミングを決めると安心です。

到着時間だけでなく参列時の立ち振る舞いも気になる場合は、通夜のマナーを徹底解説で参列時の具体的な注意点や作法を確認できます。

盛籠料の費用相場と手配方法
盛籠料の費用相場は、通常5,000円から30,000円程度となっています。
贈る相手との関係性や地域の慣習により異なる場合があります。
| 関係性 | 費用相場 |
|---|---|
| 親族 | 10,000円〜30,000円 |
| 友人・知人 | 5,000円〜15,000円 |
| 会社関係 | 10,000円〜30,000円 |
手配は、葬儀社が提供するサービスを利用するか、専門店に注文するのが一般的です。
盛籠を含めた葬儀全体の費用感を把握したい場合は、オプション別の目安が載っている葬式費用の平均相場もあわせてご覧ください。

盛籠料を支払う際に確認すべきポイント
盛籠料を支払う際には、以下の点を確認することが重要です。
まず、該当する宗教や宗派のマナーを確認し、それに合った品物を選ぶことです。
次に、盛籠を贈るタイミングや手配方法を事前に把握しておくことで、スムーズな連絡や配送が可能になります。
最後に、適切な金額と敬意を表せるよう、事前に市場調査を行い、相場を理解しておくことが肝心です。
供物としての扱いや相場についてさらに詳しく知りたい方は、金額やマナーを整理した供物料の基本と相場の記事が役立ちます。

手配を葬儀社に依頼することを検討している方は、葬儀社の選び方で業者選定のチェックポイントや注意点がまとまっているので参考にしてください。
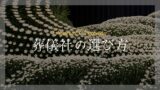
盛籠料の正しい書き方と表書きの選び方

盛籠料は、お通夜や葬儀の際に供える供物料として重要な役割を果たします。
そのため、正しい書き方や表書きの選び方を知っておくことが大切です。
このガイドでは、盛籠料の袋選びから、表書きや名前の書き方について詳しく解説します。
盛籠料の袋の選び方:白無地封筒の使い方
盛籠料を包むための袋として一般的に用いられるのが、白無地の封筒です。
白無地封筒はシンプルであり、厳粛な場である葬儀に適しています。
封筒を選ぶ際は、封筒の材質にも注意を払い、しっかりした紙質のものを選ぶようにしましょう。
封筒のサイズは、通常の長形サイズが一般的です。封筒の裏側に金額を書き入れる欄を設けておくと、受け取った側にもわかりやすくなります。
濃黒墨を使った表書きの書き方手順
表書きには濃黒墨を使用するのが一般的です。これは、哀悼の意を込めた正式な書き方とされています。
表書きを書く手順は以下の通りです。
- 墨はしっかりと滲ませずに書けるものを選ぶ。
- 封筒の中央に「御盛籠料」と書く。
- 表書きが書けたら、再度内容を確認し、誤字がないかを確かめる。
この手順を守ることで、より丁寧な印象を与えることができます。
名前の書き方と記載順序の注意点
盛籠料の封筒に名前を書く際は、封筒の左下に記載します。宛名と同様に、濃黒墨を使用するのが良いでしょう。
また、名前を書く際の順序も重要です。個人で出す場合は自分のフルネームを、団体で出す場合は団体名のあとに代表者名を書くのが一般的です。
場合によっては、以下のように記載することもあります。
| 状況 | 記載例 |
|---|---|
| 個人の場合 | 山田 太郎 |
| 会社名を記載する場合 | 株式会社〇〇 代表取締役 山田 太郎 |
名前を書く際は、読みやすい字体を心がけ、受け取った方に失礼のないようにしましょう。
盛籠を贈る際のマナーと注意すべきこと

盛籠は、法事や通夜、お葬式などで故人を偲び、遺族をいたわるためのお供え物として重要です。
しかし、その贈り方にはいくつかのマナーや注意点があります。
ここでは、盛籠を贈る際の具体的なポイントに焦点を当て、遺族に失礼がないような配慮について確認していきます。
お供え物の辞退をされた場合の対応方法
盛籠を贈ろうとした際に、遺族からお供え物を辞退されることがあります。
このようなときは、遺族の意向を尊重することが大切です。
辞退された場合、無理に送ろうとするのではなく、丁重に弔意を伝える方法を考えましょう。
例えば、心のこもったお悔やみの手紙を送ったり、後日落ち着いた時期にお花を贈ったりすることも適切です。
事前に確認するべき宗教や宗派の情報
盛籠を贈る際には、故人や遺族の宗教・宗派を事前に確認することが重要です。
宗教や宗派によって、受け入れられるお供え物が異なります。
- 仏教の場合:果物やお菓子が一般的です。
- 神道の場合:米や酒、魚が適していることがあります。
- キリスト教の場合:花が主なお供え物となります。
事前に葬儀や法要の主催者に確認を取り、相手の宗教・宗派に適したものを選ぶよう心がけましょう。
香典と盛籠の同時準備のポイント
香典と盛籠を同時に準備する際は、バランスを考慮する必要があります。
両方を贈る場合、相手に負担をかけないよう、どちらも控えめな内容にするのがおすすめです。
| 項目 | 贈る際の注意点 |
|---|---|
| 香典 | 相手の経済状況や会場の規模に応じた額にする。 |
| 盛籠 | 大きさや種類を過度に豪華にせず、相手の宗教に合ったものを選ぶ。 |
両者の品や金額を適切に調整し、遺族に負担をかけないよう心を配ることが大切です。
かけ紙やのし紙の正しい選び方と付け方
盛籠にはかけ紙やのし紙をつけるのが一般的ですが、その選び方にもルールがあります。
葬儀の場合、白黒または双銀の水引を使用し、上書きは「御供」や「御霊前」とします。
地域や宗派によっては異なる場合があるため、地元の習慣を調べておくと安心です。
かけ紙は、箱の正面から見て右側に付けるのが基本です。
かけ紙に名前を記載する際はフルネームで書き、見やすく丁寧に書くように心がけましょう。
のし紙以外にも包み方や袋の選び方が気になる場合は、用途別の実例をまとめたお布施袋の種類と選び方を確認してみてください。

袱紗や包み方との関連で実務的な取り扱いを知りたい場合は、用途別に解説した掛け袱紗の魅力と使い方徹底解説を参照するとわかりやすいです。

盛籠を贈られた場合のお返しマナー

盛籠を贈られた際には、しっかりとした感謝の気持ちを伝えることが大切です。
一般的に盛籠は、とても真心のこもった贈り物ですので、お返しのマナーをしっかり守ることで、お互いに気持ちよく良好な関係を築くことができます。
盛籠を受け取ったときの感謝の示し方
まず最初に、電話やメールで早めに感謝の気持ちを伝えることが大切です。
盛籠が届いたら、贈り主の方に一報を入れ、「ありがとうございます。」と伝えましょう。
直接会えた際には、口頭で改めてお礼を述べるとより心が伝わります。
また、感謝の印として、お礼の品を贈ることも一般的です。
贈る品については、贈り主の好みや関係性に応じて選定すると良いでしょう。
例えば、日常的に役立つちょっとしたグッズや美味しいスイーツなどが喜ばれることが多いです。
お礼状の書き方や郵送での実務的な手順を確認したいときは、会葬御礼を郵送で贈るときの基本情報が具体例つきで役立ちます。

盛籠のお返し相場とお礼状の書き方
盛籠に対するお返しの品は、通常その盛籠の約半額から3分の1程度を目安とすることが一般的です。
贈る際は、贈り主の嗜好を考慮しながら、相手が喜びそうなアイテムを選びましょう。
以下に、人気のお返しの品をリストアップしました。
- 高級感のあるバスタオルセット
- 上質な紅茶やコーヒーのセット
- グルメなスイーツセット
また、お礼状を書く際には、できるだけ丁寧な言葉で気持ちを綴ることが大切です。その際、以下のような構成で書くと良いでしょう。
| お礼状の構成 | 内容 |
|---|---|
| 冒頭 | 感謝の気持ちを述べる |
| 本文 | 盛籠を受け取った際の感想や喜び |
| 締めくくり | 再度感謝の意を示し、今後の関係の願いを込める |
お礼状は手書きで書くと一層心が伝わりますが、現代ではメールでのお礼も一般的に行われています。
どちらの方法でも、相手への感謝の気持ちを具体的に伝えることが一番大切です。
盛籠料の書き方を正しく理解し故人を偲ぶ

盛籠料は、葬儀の際に故人への感謝や哀悼の意を表すために贈る重要な品です。
この贈り物は、その場にふさわしい形で届けることで、故人やその家族への敬意を示すことができます。
書き方や贈り方に迷うことがあるかもしれませんが、その基本を押さえることで心をこめて故人を偲ぶことができます。
具体的な手順として、まずは盛籠料の用途やその地域特有の習慣を理解し、適切な形式で贈るようにしましょう。
また、金額に関しては相場を調べ、それに見合った額を選ぶことが大切です。
心を込めたお困りで、故人への哀悼の意をしっかりと伝えることができます。



