最近、葬儀や法要の場で「長寿銭とは何か」と疑問に思う方が増えています。
大切な儀式の中で手渡される長寿銭には、単なる金銭以上の意味や、ご縁を大切にする日本人ならではの想いが詰まっています。
しかし、正しい意味や使い方が分からず戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、長寿銭の基本から金額ごとの象徴的な意味、そして最新の風習や実際のマナーまで、誰でも分かりやすく解説します。
長寿銭とはどんな風習であり、なぜ大切にされてきたのか、その全貌を知りたい方はぜひ続きをご覧ください。
長寿銭とは何か

長寿銭は日本の伝統的な風習の中で、人々が長寿を願い贈り合う特別なお金のことを指します。
地域によってはお祝い事や節目の際に贈与され、その人の健康や長生きへの願いが込められています。
お金そのものに価値があるだけでなく、贈る側と贈られる側の間に生まれる温かい交流も大切にされています。
長寿銭の読み方と基本的な意味
長寿銭の読み方は「ちょうじゅせん」です。
これは、「長寿」を願う意味が強く込められている名前です。
特に、人生の節目や長生きのお祝いの際に贈られることが多いです。
単なる金銭的価値ではなく、「相手の健康と幸せを祈る気持ち」も一緒に贈る、という意味合いが根付いています。
長寿銭の歴史と風習の背景
長寿銭の起源ははっきりしませんが、古くから日本各地で長寿祝いや賀寿の儀式の際にお金を贈る習慣が存在していました。
特に60歳の還暦や70歳、77歳、88歳など、節目となる年齢を迎えた方への長寿祝いで用いられることが多くなっています。
この風習には「長く健康でいてほしい」という家族や地域社会の願いが込められています。
また、贈る時には新札やご祝儀袋を使うなど、丁寧な形で行うことが一般的です。
長寿銭と同様に歴史的な銭の意味や葬儀での扱いを詳しく知りたい方は、六文銭はいくらの価値があるのか徹底解説で由来や儀礼上の取り扱いまで丁寧に紹介されています。
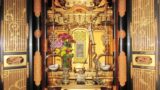
長寿銭が見られる地域と文化的な違い
長寿銭の風習は日本全国で見られますが、地域によって呼び名や贈るタイミング、形式に違いがあります。
例えば、東北地方では昔から「長寿祝い」とともに現金を包む習慣がありますし、関西地方でも「賀寿銭」と呼ばれることもあります。
地方ごとの特徴を以下にまとめます。
| 地域 | 呼称 | 贈る機会・特徴 |
|---|---|---|
| 東北地方 | 長寿銭 | 60歳・77歳・88歳などの節目に贈る |
| 関西地方 | 賀寿銭 | 還暦や米寿、地域の敬老会で贈られることが多い |
| 九州地方 | 寿銭 | お祝い膳とともに渡す風習がある |
このように、どの地域でも「長寿を願う気持ち」は共通していても、細かな違いがみられます。
地域ごとの風習の違いを具体的に把握したい場合は、当地での慣習やお墓参りの作法をまとめたお盆のお墓参りの正しいやり方とマナーも参考になります。

長寿にあやかる他の類似風習
長寿銭の他にも、長寿を祝うための日本独自の風習はさまざまに存在します。
代表的なものを下記に挙げます。
- 還暦祝い:60歳を祝う節目の行事で、赤いちゃんちゃんこを贈るのが一般的です。
- 白寿祝い:99歳を祝うお祝いで、特別なお膳や記念品を贈ります。
- 米寿祝い:88歳の米寿には、金色を使った贈り物やお祝いの席が設けられます。
- 敬老の日:全国規模で長寿を祝う日で、各地で記念イベントやプレゼントの贈り合いが行われます。
これらの風習はいずれも「長生きすることが幸せ」とされる日本人の価値観の表れだと言えるでしょう。
長寿銭はその一部として、今も大切に伝えられ続けています。
長寿銭の金額とその象徴的な意味

長寿銭は、特定の硬貨を使って長寿や健康、縁起を願う日本独自の風習です。
それぞれの硬貨には異なる意味合いや願いが込められており、贈る側と受け取る側の心が通う素敵な文化といえます。
金額によって象徴する内容が異なるため、目的や相手に合わせて選ぶ楽しさもあります。
5円玉:縁を繋ぐ願い
5円玉は「ご縁がある」ことから、縁結びやさまざまな人とのつながりを願う意味があります。
長寿銭に5円玉を選ぶことで、健康な長寿とともに、周囲の人々との縁が円満に続くようにとの気持ちが込められます。
また、新たな出会いや良い出来事とのご縁を願う時にもよく用いられます。
- 家族や友人とのつながりを大切にしたい場面にぴったり
- お祝いごとや感謝の気持ちとしても贈りやすい
- 人生の節目や記念日の贈り物として人気
10円玉:十分な長寿への願い
10円玉には「十分に長生きしてほしい」という意味が込められています。
「十」や「十分」という言葉が、すべてが満たされる様子や、健康と繁栄を表現しています。
10円玉を長寿銭として贈ることで、幸せで豊かな人生を願う気持ちを伝えることができます。
| 金額 | 込められた願い | 贈るシーン |
|---|---|---|
| 10円 | 健康・十分な長寿 | 敬老の日や誕生日 |
50円玉:五重のご縁とその信念
50円玉は「五重のご縁」と呼ばれ、5円玉よりもさらに強い縁や幸運を願う意味が含まれています。
穴の開いたデザインも特徴的で、幸せが巡り続けることを象徴しています。
人生において、さまざまな良いご縁や幸運が五重に広がることを願うときにぴったりの硬貨です。
100円玉:百のご縁に込められた意味
100円玉には「百歳まで元気に」「百に及ぶご縁」といった、より大きな長寿や縁起の意味があります。
長寿銭として贈れば、特別な節目や大切な人への強い思いを表現しやすいです。
親しい親族やお世話になった方への贈り物によく選ばれています。
500円玉:最大の長寿への願望
500円玉は、日本の硬貨の中で一番大きな金額であることから、「最大限の長寿」「これ以上ない幸せ」を願う特別な意味があります。
敬意や感謝の気持ちを最大限伝える贈り物として最適です。
特に還暦や米寿など、人生の大きな節目を迎える方に贈ると喜ばれます。
葬儀における長寿銭の準備と配り方

長寿銭は、一般的にお祝いの場面で使用されるイメージが強いですが、地域によっては葬儀や法要の際に配る風習も見られます。
主に喪主や遺族が参列者に対して感謝や無事を祈る気持ちを表して配る場合が多いです。
そのため、事前にマナーやルールを知っておくことが大切です。
長寿銭を準備する際の注意点
長寿銭を用意する場合、まずは地域や宗教・宗派ごとの風習を確認することが大切です。
金額は基本的に小額とされることが多いですが、適切な金種や枚数にも決まりがある場合があります。
新札ではなく、流通している比較的きれいな旧札を選ぶ方が無難です。
また、手配するタイミングも重要で、葬儀の準備段階で早めに用意しておきましょう。
- 親族など儀式に詳しい方に相談する
- 金融機関や郵便局で両替をしておく
- 予備も含めて余裕を持った数を準備する
葬儀や法要に合わせた準備全体の流れを把握しておくと安心です。手続きや段取りを整理したい方は、葬儀後にやることリストや手続き一覧表をチェックしておくと役立ちます。

のし袋や包装の選び方とマナー
長寿銭を包む際には、地域によって異なる場合がありますが、基本的にはシンプルな白い封筒や、無地の袋が使われます。
派手な柄やカラフルなデザインは避け、落ち着いたものを選びましょう。
表書きには「長寿銭」や「無病息災」など、適切な言葉を書きます。
下記は、よく使われる包装と適切な表書き例です。
| 包装の種類 | 表書きの例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 白封筒 | 長寿銭 | 装飾を避ける |
| 半紙包み | 無病息災 | 薄墨で書く場合も |
| のし袋(無地) | 御礼 | 慶事用の熨斗や水引は使わない |
表書きや包み方に迷ったときは、封筒の水引や印刷の選び方を詳しく解説した香典袋の水引と印刷による選び方を参照すると具体的な判断基準がわかります。

配る際に考慮すべき年齢のガイドライン
長寿銭を配る対象年齢や範囲も、地域や慣習によって異なります。
一般的には、葬儀や法要に参列した子どもや若い世代に配るケースが多いです。
大人全員に配る風習の地域もあれば、子どもや学生のみが対象となる場合もあります。
- 小学校以下の児童:必ず配るケースが多い
- 中・高校生:配る場合と配らない場合がある
- 成人以上:配らないことが一般的
迷った場合は、地域の年長者や葬儀を取り仕切る方に相談すると安心です。
周囲への配慮も忘れず、温かい気持ちを込めてお渡ししましょう。
長寿銭を受け取った後の使い方

長寿銭を受け取ったあとは、その価値や意味を存分に活かせる使い方を選ぶことが大切です。
古くから伝わる長寿銭は、健康や長寿を願う心が込められているため、自分や大切な人のために役立てられます。
お守りとして持ち歩く方法
長寿銭はお守りとして日常的に持ち歩くことで、健康や安全を願うお守りの役割を果たします。
財布や鞄、ポーチの中に入れておくだけでなく、家の玄関や寝室など大事な場所に置く方もいます。
- 財布に入れて金運や健康運アップを願う
- カバンに忍ばせて毎日持ち歩く
- 家の神棚や玄関に飾る
- お守り袋などに入れて肌身離さず持つ
身近に長寿銭があることで安心感が得られるでしょう。
大切な人への贈り物にする方法
長寿銭は、親や祖父母、親しい友人など大切な人への贈り物としても人気があります。
特に還暦や米寿、敬老の日などの節目のお祝いにぴったりです。
| 贈る相手 | おすすめのシーン | ポイント |
|---|---|---|
| 両親・祖父母 | 長寿のお祝い、健康祈願 | 手紙やメッセージを添えると喜ばれます |
| 友人 | 誕生日や人生の節目 | オリジナルの小袋に入れて贈るのがおすすめです |
| ビジネス関係 | 取引成立や節目の挨拶 | 縁起物として感謝の気持ちを伝えられます |
贈る際は、長寿銭の意味を説明するとより心のこもった贈り物になります。
買い物での活用とその影響
一部の地域や伝統的な店舗では、長寿銭を特別な日や節目の買い物に使用する風習があります。
これは、ご利益や縁起担ぎの意味合いがあります。
また、長寿銭を財布に入れて使わずに持ち歩くことで、金運が上がるとされているところもあります。
実際の買い物で使う場合は、記念日などに特別な商品を購入する際や、お守り代わりに使われることが多いです。
このような習慣が、その人や家族などにも良い効果をもたらすと昔から伝えられています。
寄付・供え物としての活用方法
長寿銭は、神社やお寺へのお賽銭、慈善活動への寄付、先祖へのお供え物としても活用されています。
ご利益を分かち合うという思いが込められるため、自分だけでなく多くの人やご先祖さまへの感謝の気持ちを表すのにぴったりです。
供え物としての場合、家族の繁栄や健康、長寿を願う場面で多く使われます。
寄付をすることで、善意の輪が広がり、自身にもよい運が巡ってくると信じられています。
寺社への供え物や寄付を考える際、参拝やお経にかかる費用を把握しておくと安心です。費用の目安や当日の流れはお寺でお経をあげてもらう費用目安で確認できます。

長寿銭とは何か、その意義と未来展望

長寿銭とは、健康寿命の延伸や高齢社会における新たな課題の解決を目的とした、社会的・経済的な概念です。
具体的には、高齢化によって増大する医療費や介護費などの社会保障費を、より持続可能な形で支え合うための金融や保険の仕組み、あるいは新しいサービスや商品開発の動向を指します。
長寿社会が進行する中で、誰もが安心して長生きできる社会を作るために、お金のあり方や使い方が見直されているのです。
近年では、長寿銭をいかに効率的に運用し、自立したシニアライフをサポートできるかが注目されています。
また、個人だけでなく、地域や企業による高齢者向けのコミュニティづくりや、健康増進プログラムの開発など、幅広い分野で活用の機運が高まっています。
今後、少子高齢化がさらに進む日本において、長寿銭は社会の安定や発展のためにますます重要な役割を担っていくでしょう。
新しい価値観に基づくお金の使い方や、心豊かに生きるための仕組みづくりが未来展望として求められています。


