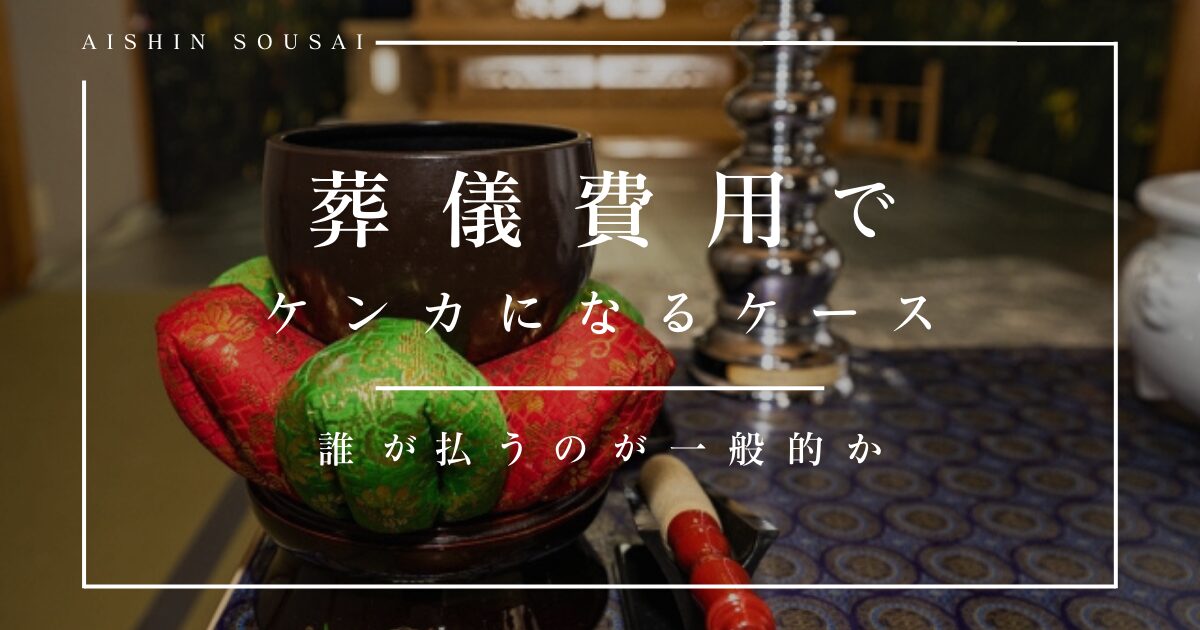故人を見送るための大切な儀式であるお葬式ですが、人生のなかで喪主や施主を務める機会は多くなく、その対応に疑問や不安を感じるものです。
そのなかでも、葬儀費用を誰が支払うのかを決めることは、金銭が関わることからトラブルや遺族間でのケンカに発展することも珍しくありません。
このように無用なトラブルを起こさず、スムーズに葬儀を執り行うためには、葬儀費用を誰が払うものか事前にポイントを押さえておくことが重要です。
葬儀費用でケンカになる5つのケース

葬儀は家族にとって大切な儀式ですが、その費用を巡っては様々なトラブルが生じることがあります。
具体的にどのような問題でケンカになってしまうのか、具体例を見ていきましょう。
葬式の規模に関する意見の相違
親族間で葬式の規模に関する意見が異なるケースは珍しくありません。
一部の家族は故人の社会的地位や交友関係を考慮し、大規模な葬儀を望むことがあります。
しかし、今後の生活を心配する家族もおり、家計に大きな負担をかけないよう小規模なものを希望することも。
この意見の相違は、まさに喧嘩の火種となり、一致した決定に至るまで多くの話し合いが必要になるでしょう。
式の規模を縮小する選択肢や、費用を抑える際の注意点を知りたい方は、直葬を選ぶ理由とお金がないときの対策で現実的な選択肢とメリット・デメリットを確認できます。
https://www.aishin-sousai.com/3357
高額な葬儀プランへの賛否
葬儀費用は、プランによって大きく異なります。高級な棺や設備、特別な儀式を含むプランは、それに見合った料金がかかります。
保険の受取人である配偶者や子供は高額な葬儀プランを選ぶかもしれませんが、ほかの家族はその出費が家計に大きな打撃を与えると考え、不満をもつことがあります。
将来のための貯金を守りたいと考える者と、故人に最後の敬意を表したいと考える者との間で、意見が分かれてしまうのです。
追加サービスの必要性を巡る議論
葬儀で提供されるオプションや追加サービスも、議論の種になります。
例えばビデオ撮影や追悼のスライドショーなどは、故人を偲ぶ上で大切な演出と捉える家族もいれば、必要ないと感じて追加料金を払うことに消極的な家族もいるのです。
ビデオ撮影や追悼演出などのオプションをどう扱うか迷ったら、遺骨の取り扱いや選べる対応を詳しく紹介する火葬場で残った骨はどうするの記事が参考になります。
https://www.aishin-sousai.com/3548
遺族以外の参列者の扱いに関する意見の違い
祖父母や親戚、故人の友人など、遺族外の参列者の扱いも意見が分かれる要因です。
一人一人に対してどの程度のフォローをすべきか、会食の席を用意するべきかどうか、といった具体的な対応について家族間で不満が噴出することがあります。
費用分担の不均衡
家族の一員を失った悲しみに加え、葬儀費用の負担が不均衡であることが親族間の不和の種になることがあります。
喪主と親族が周りの経済状況を考慮せず、高額な料金の葬儀を強行。これに対して、ほかの兄弟や姉妹は不満をもつケースは本当に多くあります。
例えば長男の家庭は家計が厳しいにも関わらず、「長男だから」という周りの意向で葬儀費用の一番大きな割り当てを強いられるケースです。
葬儀社によって記載された見積もりをもとに、各家族の経済状況を考慮し、話し合いによって公平な分担を目指すことが一切の問題を解決するためには重要です。
例えば「誰がどれだけ払うか」を巡って不満が出やすい局面については、立場別の対処法をまとめた嫁いだ娘でも親の葬儀代を出すべきで具体的な事例と解決策を確認できます。
https://www.aishin-sousai.com/2529
葬儀費用は一般的に誰が払う?

葬儀費用の支払いは誰が行うべきかを考える際、葬儀の主宰者である「喪主」への理解が重要なポイントです。
ここでは葬儀費用は誰が払うのか、様々な立場から解説します。
喪主
葬儀費用の支払いは、葬儀の主宰者である喪主が全額負担することが一般的です。その理由として、日本の文化や法律、社会的慣習に根ざしていることが挙げられます。
日本においてお葬式は家族や親族が中心となって執り行われることが多く、喪主は遺族の代表として配偶者や子どもである長男長女が務めることが一般的です。そのため、費用も家族や親族が負担することとなり、法律上「喪主が支払わなければならない」という規定はありませんが、それでも葬儀を取り仕切る喪主が責任を負うことが多いのが現状です。
また、社会的慣習においても、喪主が葬儀費用を負担することが望ましいとされています。例えば葬儀や法要では喪主が主役となり、親族や友人たちが喪主を支えることが一般的です。そのため、葬儀費用を喪主が負担することで、周囲からの支援や協力が得られやすくなるとされています。
このような理由から葬儀費用の支払いを喪主が行うケースが多いですが、必ずしも喪主が支払うべきルールがあるわけではないことを覚えておきましょう。
喪主や施主の役割分担で悩む場合は、誰にどの役を依頼するかの判断基準や配慮点をまとめた喪主と施主の決め方を一読しておくと判断がスムーズになります。
https://www.aishin-sousai.com/3347
兄弟
遺族の中に十分な財産がなかった場合や、故人が亡くなった時点で借金があった場合など、葬儀費用を喪主一人で負担することが困難なケースは珍しくありません。
このように、葬儀によって遺族の負担が大きくなることを防ぐため、葬儀費用を兄弟姉妹で分担することもあります。
その際には一律で分担するのではなく、遺産分割の割合や経済状況を鑑みて、それぞれ負担する金額を決めることが自然な流れであるといえるでしょう。
施主
施主とは「お布施をする主」という意味合いのとおり、葬儀費用を支払う人のことを指します。
喪主をはじめ遺族が葬儀費用を支払うことが一般的ですが、故人自身が葬儀費用を負担する旨を遺言書や生前に準備しておいた「葬儀社担当者選任書」で示していた場合、施主が葬儀費用を負担することになります。
具体的には、故人が自身の死後における葬儀費用を負担する旨を遺言書や葬儀社担当者選任書で定めており、その人が施主となります。この場合、遺族は葬儀費用を負担する必要がありません。
ただし、遺言書や葬儀社担当者選任書がない場合や、故人自身が葬儀費用を負担する旨を定めていたにもかかわらず故人の財産が不足している場合は、遺族が負担することになるため注意が必要でしょう。
相続人
葬儀費用は故人の遺族が負担することが一般的ですが、これは遺族が相続人であるケースが多いことが理由に挙げられます。相続人が複数人いる場合には、それぞれ相続する金額の割合から計算して、分担する葬儀費用を決めるとトラブルも防ぎやすいでしょう。
なお、故人の財産を相続する際には相続税が発生しますが、相続財産から葬儀費用の支払いを行った場合は、発生した費用を控除対象とすることができるため、節税対策にもなります。
相続財産は墓石費用や香典返しなどの支払いに使用できないという制限もあるため、事前確認は必ず行いましょう。
葬儀費用で親戚とケンカにならない心得
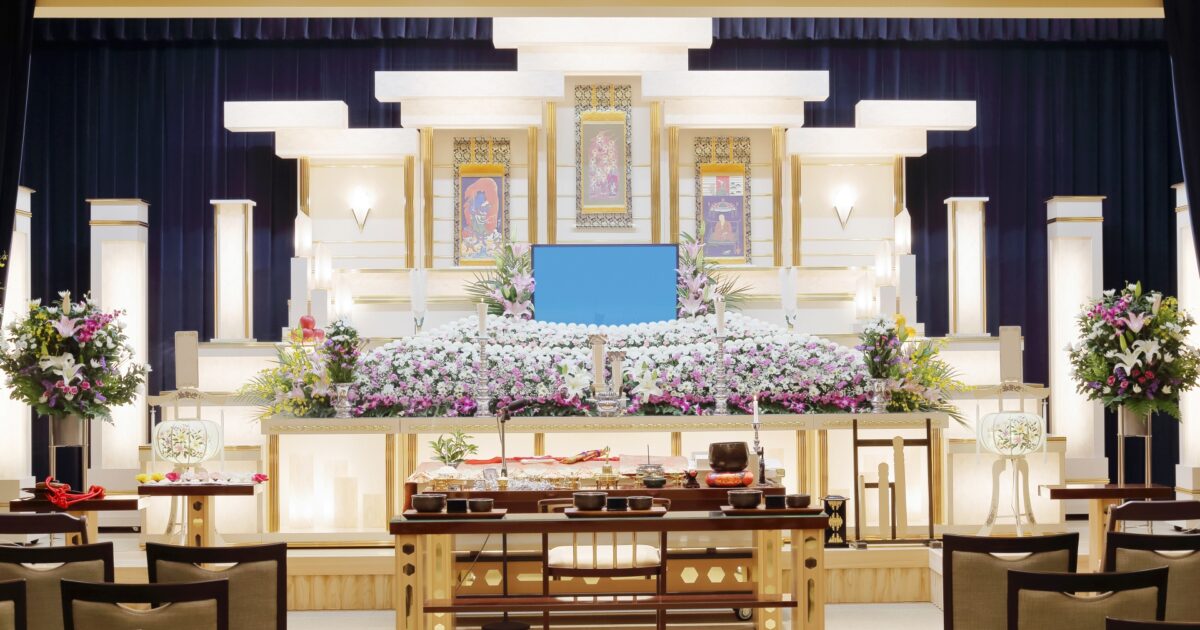
葬儀費用は喪主が負担することが一般的ですが、法的に定められているものではなく、親族をはじめ複数人で負担しても問題ありません。しかし、金銭が絡む内容でもあるため、ケンカやトラブルも起こりがちです。
ここでは、無用な揉め事を引き起こさないための方法について紹介していきます。
本人との話し合いは必須
葬儀費用を分担して支払う場合、負担する本人との話は必須であり、内容に納得してもらった上で準備することは非常に重要です。
親族との仲が良好だからといって、十分な協議を行わず葬儀費用を請求することはもちろん「支払ってくれて当然」というスタンスでいると、トラブルの原因となります。
葬儀費用の負担額だけではなく、状況に応じて葬儀内容や規模などについても相談し、内訳にも合意を得た上で準備を進めると、揉め事を回避しやすいでしょう。
話し合うべき項目
葬儀費用を複数人で負担する場合、単に総額を伝えて負担する人たちで分割すれば良いわけではありません。
葬儀は規模や内容によって発生する費用が大きく異なるため、喪主が独断で進めてしまうと、金額によって「そんな規模でやらなくてもいいのでは?」「安いプランにすべきでは?」など反発されることも起こり得ます。
こうしたトラブルを回避するためには、協力を求められる立場で考えることが重要です。
事前相談することはもちろん、「香典は誰が受け取るのか」「どのように分配するのか」など、話し合う項目を明確にしておくと後々のトラブルも防げるでしょう。
助け合い
相手の立場を考慮せずに葬儀費用を均等に負担することを求めることは、揉め事の火種になりかねません。
同じ親族だからといって、家庭の有無や貯蓄金額、収入をはじめとする経済状況は人によって異なります。経済状況が芳しくない人に大きな金額を負担するよう求めれば、トラブルが発生することは明らか。
また、経済的に苦しく、「親の葬儀費用が払えない」といった事情から周囲に助けを求めることもあるでしょう。
葬儀費用の負担がほかの人よりも少額となる場合には、斎場の予約や手続き、参列者への連絡といった金銭の負担以外のことを率先して行い、関係者の負担を減らすよう立ち回ることも重要です。
地域の斎場や相場を調べるほか、葬儀社に電話連絡や契約手続きを進めることは時間と手間がかかります。お葬式費用をほかの人に多く出してもらう分、お金がかからないことで役立とうとする考え方も、周囲の心象を良くするものです。
このように、無用なトラブルを起こすことなく、故人を気持ちよく送り出すためにも、関係者同士助け合う気持ちで準備を行いましょう。
葬儀費用を安くする方法

葬儀は一般葬で100万円程度かかるといわれており、故人を見送るものとはいえ、貯金や相続をする財産の金額によっては、なるべく費用を抑えたいと考える人もいることでしょう。
ここでは、葬儀費用を安くする方法を紹介していきます。
故人の貯金から支払う
葬儀費用の支払いを、故人の貯金をはじめとする遺産から支払う方法があります。
喪主や施主自身の経済的負担を軽減できることはもちろん、金額によってはすべて賄えることもあるでしょう。
また、相続財産から葬儀費用の支払いをした場合、その金額は相続税の控除対象となるため、節税対策としても効果的です。
葬儀費用だけではなく税金の支払いも抑えたい人は、要チェックな方法であるといえるでしょう。
葬儀の規模を縮小する
葬儀費用を抑えたい人は、葬儀そのものの規模を見直すことも方法のひとつです。
例えば一般葬は故人の親族や友人、知人など広く一般に公開された形式であり、多くの人々が参列するの葬儀です。式場を借りて葬儀を行い、冠婚葬祭業者も交えて下記のような内容が行われます。
- 祭壇
- 弔問台
- 遺影写真
- 供花
- 音楽演出
など
また、参列者に飲食物や追善会の招待が行われることもあるため、葬儀費用は高くなりがちです。
一方、家族葬は、故人の遺族や近親者、または限られた人数のみで行われる葬儀です。
そのため、自宅や葬儀場の小規模な式場などで行われ、参列者には遺族や近親者のみが招待されることが多く、飲食物や追善会は行われないことも珍しくありません。
葬儀の形式や内容は、故人や遺族の希望によって変わるため、必ずしも一概に費用が安くなるわけではありませんが、一般葬と比べて家族葬は参列者が限られているため費用が抑えやすいです。
そのほか、告別式を行わず火葬のみを執り行う直葬であれば、さらに費用を抑えることが可能です。
このように、葬儀の規模を縮小することで葬儀費用は抑えられるため、故人の意向を考慮しつつ検討してみると良いでしょう。
制度を活用する
葬儀費用は、年金制度や葬祭扶助制度といった制度利用をすることでも負担を軽減することが可能です。
年金制度では加入している種類によって受けられる制度が異なり、申請することで一定金額を受給できます。
| 国民年金の場合 | 厚生年金の場合 |
|---|---|
|
|
葬祭扶助制度は生活保護受給者自身の葬儀や、生活保護受給者が葬儀を行う際に、負担を軽減するために自治体から支給される制度です。葬儀前に申請を行う必要があるほか、対象者に制限があるため年金制度の利用の方が一般向けであるといえます。
なお、生活保護受給者であっても周囲からお金を集めることができる人は、支払い能力があるとみなされ、制度利用ができないことにも注意しましょう。
葬儀社を相見積もりする
葬儀費用を抑えるためには、複数の葬儀社から相見積もりを取ることも効果的です。
同じ故人を見送る儀式であっても、依頼する葬儀社によって用意されているプランや規模が異なります。1社からの見積もりだけではなく、複数社から見積もりを提示してもらうことで、同じ内容でも安いプランを見つけられる可能性があります。
お葬式の手配はすることは人生において頻繁にあることではなく、多くの人が戸惑うものです。
見積もりの依頼は無料で行えるため、不安や疑問があれば周辺エリアの葬儀社へ気軽に問い合わせてみると良いでしょう。
複数社で見積もりを比較するときのチェックポイントや交渉のコツは、実務的な手順を解説した葬儀社の選び方で分かりやすくまとまっています。
https://www.aishin-sousai.com/261
葬儀費用は相続税から控除が可能

故人に遺産があり、それを相続する際には相続税が発生しますが、相続する財産から葬儀費用を支払うことで節税対策も可能です。
ここでは、葬儀費用の支払いにおいて、相続税の控除対象と非対象について解説していきます。
控除できる費用
相続税から控除できる葬儀費用は、基本的に一般葬を行うために必要な費用が対象となります。いくつか例を挙げると、下記のような通常の葬儀に欠かせないものが挙げられます。
- 遺体回収費用
- 火葬費用
- 埋葬費用
- お通夜費用
- 読経料
なお、相続人以外が支払いをしたものにおいては、当然対象となりません。
遺産相続する際には総額から控除額を差し引いて申告書を作成するため、領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
控除できない費用
「故人を見送る儀式」という括りで考えると迷ってしまいますが、香典返しや初七日、法事などでかかった費用は相続税から控除することができません。墓石の購入や、墓地を借りるためにかかった費用においても同様です。
遺体の回収から火葬・埋葬までの費用は控除対象、葬儀後の対応や墓石の購入といった葬儀に直接関係しないものは控除対象外と考えると分かりやすいでしょう。
葬儀費用は喪主が払うケースが多いものの話し合いは必須

葬儀費用は、社会慣習の観点から喪主となる人が支払うことが多いです。しかし、法的に喪主が支払わなければならない決まりはなく、規模や内容によっては費用を複数人で負担することも珍しくありません。
こうした金銭のやり取りではトラブルに発展することも多く、関係者とは必ず事前に話し合うことをおすすめします。また、葬儀費用は相続税の控除対象にすることもできるため、知識を共有することも重要です。
葬儀の準備は人生において頻繁に発生するものではなく、不安や疑問がついて回ります。スムーズに執り行うためには、専門家である葬儀社に相談して解決するのもポイントです。
故人を見送る儀式をスムーズに執り行うためにも、ぜひ本記事を参考にしてください。